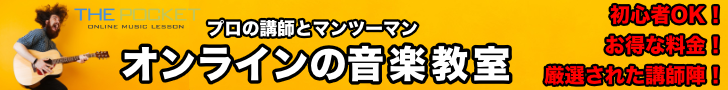音楽の調味料=コード進行
音楽の顔となるのはメロディです。人は音楽から何よりもまずメロディを聴き取ります。しかしそれはメロディだけで音楽が成り立つと断言できるものではありません。
たとえば料理に置き換えてみますと、メロディはにんじんだったり、ジャガイモだったり、豚肉だったりというような「素材」に当たります。「にんじん」を食べればおおよその人はそれが「にんじん」であるとわかりますね。それは、「にんじん」には、その「にんじん」なりの味の特徴があるからです。同じように「メロディ」にも、その「メロディ」なりの特徴があります。
しかし、素材はそれだけでは料理になることができません。料理には調味料が必要です。その調味料の配合次第では、にんじんとジャガイモと豚肉の組み合わせは肉じゃがにもなり、カレーにもなります。また、同じカレーでも調味料の加減次第では辛口のカレーにも甘口のカレーにもなります。
音楽の中で調味料の役割を果たすのはハーモニー、つまりコード進行です。そしてコード進行や和音選びにはその作曲家の個性が顕著に表れるものです。画家の個性が絵具の組み合わせによる色彩に表れるのと同じように、作曲家の個性は音の組み合わせによるハーモニーに表れます。
特に女性に人気のあるアーティストであるaikoの楽曲にも独創的なコード進行がよく見られます。彼女の楽曲の特徴はそのストレートな歌詞と個性的な楽曲でしょう。今回はaikoのいくつかの楽曲におけるコード進行を中心にアナリーゼして、その特徴を探りつつ、歌詞の世界観とどのように共鳴しているのか考察してみましょう。
『ボーイフレンド』のテンションの高さとおしゃれさ
最初に取り上げる楽曲は『ボーイフレンド』です。2000年にリリースされたこの楽曲は『カブトムシ』と並んでaikoの代表的な楽曲です。この楽曲においてコード進行の観点から注目したいポイントはサビの部分です。サビは次の歌詞の範囲に該当します。
“あぁ、テトラポット登って”~“好きよボーイフレンド”
『ボーイフレンド』(作詞:AIKO)より
そして、その前半のコード進行は次のようになっています。
譜例1(Cdurに置き換えています。後の譜例も基本的にCdurに置き換えたものとなります。)

譜例を見る限りでは、際立って特徴的な箇所はなさそうです。D7→G7→Cという進行は和声法の教本に出てくるような基本的な進行です。このように基本的な、下手をすると野暮になってしまいそうなコード進行をここまでおしゃれなポップソングに仕上げているものは何でしょうか?
ここでメロディに注目してみましょう。実はこのサビにはコードとメロディで音が一致しない箇所があります。普通ならばそのようにはなりません。次の譜例を見てください。
譜例2(矢印が付いている音はそれぞれのコードに含まれていない音です。)

譜例2のように、そのコードに含まれていない音を用いつつも、基本的にはコードを構成する音が中心になってメロディは作られるものです。
しかし、『ボーイフレンド』ではコードとその上に置かれているメロディの音が一致しないのです。次の表を見てみましょう。この表にはサビの冒頭数小節のメロディの音名とコード名が記載されています。表を見ますと、D7のコードの上にはeの音が、G7の上にはesとc、dが、そしてCの上にはcの音がメロディとして乗せられていることがわかります。
表

メロディのどの音がコードを構成する音と一致しないのかチェックを入れてみましょう。
まず冒頭のD7の上に置かれる音が一致していません。D7を構成する音はd、fis、a、c。メロディに書かれているeの音は含まれていません。
譜例3

さらにその次のG7の上に置かれているメロディに注目しましょう。esはG7を構成する音ではありませんし、そもそもCdurの音階に含まれる音はesではなくeの音ですね。
譜例4

ここまで見ましたように、『ボーイフレンド』のサビにはコードには含まれないeとesの音があります。これらは一体何なのでしょうか?
まず冒頭のD7に付けられたeについて考えてみましょう。試しにD7にeを付加すると次のようになります。
譜例5

いわゆる「ナインスコード」になります。ところで、ナインスコードはテンションの高いコード、つまり「テンション・コード」です。テンションとは一般的には緊張を意味する言葉ですが、音楽においてはこの緊張を生み出すために三和音やセブンスの和音に付加された音そのものを指す場合が多いです。
譜例6

和音にテンションが加わることによって、その響きに深みや緊張感、張りが与えられます。サビのD7に付加されているeもコードを構成する音の一つであると考えるのであれば、『ボーイフレンド』のサビでは冒頭にテンション・コードが用いられていることになります。
前回までに取り上げた『空も飛べるはず』や『波乗りジョニー』の例を出すまでもなく、基本的に音楽においてサビは一番盛り上がる箇所です。『ボーイフレンド』では感情が最高潮に高まるサビの冒頭にテンション・コードが用いられ、その箇所には“あぁ”という言葉にならない思いを表出する歌詞が付けられています。テンション・コードが歌詞と合わさることによって、その歌詞の中の主人公の言葉にならない思い、溢れ出る奔放さのようなものが自然と表現されているように思えます。
では、G7に付けられたesの音はどのように解釈するべきなのでしょうか?
ここで思い出されるのは「ブルー・ノート」です。ブルー・ノートとは、長音階(メジャー・スケール)の第3音と第7音が半音下げたもので、主にブルースやジャズなどで用いられます(時には第5音も下げることがあります)。
譜例7

一般的なポップスにおいても、通常のコードの上にブルー・ノートを用いたメロディを置くことによってブルースっぽさを演出することができます。Cdurの音階上でブルー・ノートを用いると第3音のeの音がesになります。そこから『ボーイフレンド』のサビに出てくるesの音もブルー・ノートであると考えることができます。
このようにシンプルなコード進行によるサビのフレーズも、そこにテンションやブルー・ノートが付けられることによって、おしゃれな雰囲気に仕上げられています。さらに、サビのテンションの高さは歌詞の内容と共鳴することによって、歌詞そのものの世界観をより具体的に表現することができていると考察することもできます。
メジャーコードとマイナーコードのコントラスト
続けて取り上げる楽曲は『ロージー』です。そのイントロ直後の歌詞は次のようになっています。
“運命には逆らえないね”
『ロージー』(作詞:AIKO)より
この歌詞に当てられているコード進行は次の通りです。
譜例8

“運命には逆らえないね”の“いね”の部分にはGmが当てられています。Cdurの中でGmが出てくることは特殊なことです。それは次のようにGmに含まれるbの音が音階に含まれていないためです。
譜例9

しかし、Cdurの中でもbの音が臨時的に出てくることはよくあります。それはFdurに一時的に転調するときに出ることが多いです。なぜなら、bの音はFdurの音階に含まれていて、さらにFdurの属七の和音(C7コード)を構成する音だからです。転調する際に転調先の属和音(ドミナンテ)を用いることは、よく用いられる転調法の一つです。
譜例10

しかし、一時的にFdurに転調するならば、FM7の前はGmではなくC7にすることが普通です。
譜例11

なぜ『ロージー』ではC7ではなく、Gmになっているのでしょうか?
まず考えられることは、C7は長和音でGmは短和音であるということです。長和音からは明るい印象を受け、短和音からは暗い印象を受けますよね。
『ロージー』のGmの前後のコードはCとFM7となっており、それらはどちらも長和音で、比較的明るい印象を与えるものです。色に置き換えてみますと、たとえば白色と白色のボーダーの間に黒色のボーダーを挟むとその色の違いによってコントラストがはっきりとします。同じように、このCとFM7という明るいコードの間に、Gmの暗いコードを挟むことによってコントラストがはっきりとして印象的になります。
譜例12

さらに、この部分のリズムにも着目してみましょう。Gmが出てくる箇所はシンコペーションになっています。シンコペーションとは、裏拍を長い音符にしたり、アクセントをつけたりすることによってリズム的に強調させる方法のことですが、Gmにシンコペーションが用いられることによって、それはスパイスのような役割を果たし、このコードをより効果的に目立たせています。
「あたしの不安定さ」が現れるコード進行
最後に『桜の時』のコード進行を見てみましょう。イントロ後のメロディでは次のようなコード進行が用いられています。
譜例13

このコード進行をピアノなどで弾いてみると、どこか不思議な印象を受けるのではないでしょうか。ここで『ボーイフレンド』や『ロージー』と同じように、まずはこのコード進行で用いられている和音がCdurの音階に含まれているものかどうか調べてみましょう。
始めのCはCdurに含まれる音から成り立っていますが、問題はその次のA♭からです。このコードを構成するasとcとesのうちasとesはCdurの音階には無い音です。さらに、その次のB♭を構成する音はbとdとf。やはりCdurには含まれていないbの音があります。
譜例14

このように『桜の時』の初めのメロディでは、コードが変わるたびにその調には含まれていない音が用いられていますが、それは「平行和音」であると考えることもできそうです。平行和音とは、ある和音が形やその種類を変えずに音をそのまま平行するように移動しながら連なる進行のことです。言葉で説明すると少しわかりにくいので譜例を用いながら説明しますと、次のようなものになります。
譜例15

譜例15を見てわかるように、譜例中の☆印が付いた和音は形が展開形(いわゆる「分数コード」)になったりせずに、さらに短和音や長七の和音などに種類が変わることなく、同じ形(譜例では基本形)と種類(譜例では長三和音)を保ったまま、ただ上下に平行しています。この手法はクラシック音楽の分野でもドビュッシーやラヴェルなどの近代以降の作品に見られる方法です。つまりとてもモダンな和声法だとも言えます。
しかし、『桜の時』におけるこの平行和音はモダンさの現れというよりも、不安定さの現れと見ることが妥当なのかもしれません。と言いますのも、コードが変わるたびに調に含まれない音が出てくるというのは、調的に安定しないということでもあるからです。『桜の時』の最初のメロディで平行和音を用いることによって、楽曲のキーは安定しないものになります。
しかも、この楽曲はサビに向かうまでのメロディがコロコロと雰囲気を変えていきます。次の範囲のメロディをそれぞれ比べて聴いてみてください。それぞれのメロディの性格は異なり、雰囲気の変化が安定しません。
“今まであたしがしてきたこと”~
『桜の時』(作詞:AIKO)より
“降ってくる雨が迷惑で”~
“春が来るとこの川辺は”~
このようにサビまでの雰囲気を不安定なものにすることによって、“右手をつないで”からのサビのメロディからはより安定した印象を受けます。そして、サビはとても前向きな内容の歌詞になっています。それまで自分自身を認めることができなかった不安定な「あたし」が「あなた」に出会えたことによって前向きになれるという歌詞の内容は、不安定な雰囲気から安定した雰囲気に変わる音楽そのものにも表れていると考えられそうです。
まとめ
ポップスやロックはアメリカやイギリスで生まれたもので、それらは伝統的な和声法の影響下にありました。そのように考えてみますと、アメリカやイギリスで生まれた音楽に多少なりとも影響を受けているはずのスピッツや桑田佳祐の音楽にも伝統的な和声法のはるか延長線上にあるコードが用いられていることは不思議なことではありません。
そして日本の現在のアーティストのほとんどは、スピッツや桑田佳祐から少なからず影響を受けているでしょう。今回取り上げたaikoもその一人だと思われますが、今回アナリーゼしましたように、そのコード進行は極めて独特です。
様々な専門家の方が述べていますように、aikoの楽曲は個性的なのです。私自身も今回取り上げた『ボーイフレンド』や『ロージー』、『桜の時』以外にもaikoの様々な楽曲を実際にアナリーゼしてみましたが、音楽理論的に解釈の難しい楽曲がほとんどでした。
この解釈の難しさは何よりもaikoの楽曲の自由さに由来するのでしょう。そしてその音楽の自由さは、彼女が歌詞から先に作るいわゆる「詞先」というスタイルを取っていることに関係するのかもしれません。歌詞を先に書くことによって、その歌詞の世界観がそのままメロディとなり、コードとなり、そしてリズムとなります。その結果、歌詞と音楽の世界観がaikoの楽曲の中で深く一致するのだと感じます。
aikoの楽曲が解釈困難なものだとしても、アナリーゼの解釈とは基本的に自分自身のためのものです。自分自身がどのようにこの楽曲を解釈するのかということを大切にしましょう。
さて、今回は主にコード進行に着目しました。コード進行に注目してアナリーゼする際には次のような視点で見てみると良いでしょう。
・和音がテンションの高いものか、もしくは特殊な音(ブルー・ノートなど)が付加されているか
・そのコードを構成する音が音階に属するものであるのか
・長和音と短和音との配合のバランスに特徴はあるのか
・一般的なコード進行と異なる点はあるのか
以上の4つの視点で見た上で、リズムや歌詞などとの関係性を調べることで深い解釈ができるでしょう。皆さんもぜひaikoの好きな楽曲をアナリーゼしてみてください。